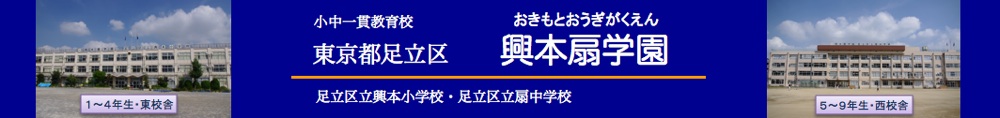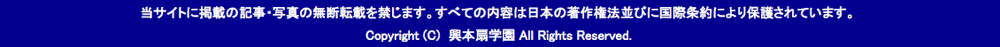興本扇学園 アーカイブ
平成18年度(2006年4月〜2007年3月)



興本扇学園の開設式が、足立区教育委員会主催で行われました。國井清伸教育委員長が主催者を代表して開設の告辞がありました。國井委員長は、本校の元PTA会長でもあり、本校の発展に大きく寄与されてきた方だけに、今回の開設には感慨深いものがあったと思われます。 次に、本校の砥抦校長から、興本小学校と扇中学校の先生たちが、どういう小中一貫教育校にしようかとこの2年間話し合いを重ねてきて、「興本扇学園」が誕生した経緯と、学園を卒業した子どもたちにこうなってほしいという夢があるという話がありました。
また、ご来賓を代表して、小中一貫教育校推進委員長として、いろいろな考えのある地域・保護者のご意見をまとめてこられた榎本栗吉町会長から励ましと期待している旨のお話をいただきました。
最後に、児童生徒の代表として、小学校と中学校の代表の二人が、この学園をみんなの力でよくしていこうという決意と呼びかけの言葉があり、開設式の最後を飾りました。
こうして、興本扇学園が船出をしました。大波小波、いろいろなことが起こる大海原に乗り出したわけですが、子ども・地域・保護者・学校・行政が一体となり、推進者にもなり、支援者ともなり、小中一貫教育の夢を実現させていきたいものです。


平成18年度 入学式式辞
一年生のみなさん、入学おめでとう。校長先生やほかの先生たちは、みなさんが入学してくるのをとても楽しみにしていました。
みなさんは今日から興本扇学園の一年生です。みんなで一緒に「おきもとおうぎがくえん」と言ってみましょうか。大きな声で言えましたね。
興本扇学園には、こういう子どもになってほしいという目標があります。全部で4つありますが、今日はその中から二つだけお話します。
一つは、「お」です。おもいやる子の「お」です。おもいやりのある子ともいいます。人に親切にできる子のことをいいます。困っている人がいたら助けてあげられる人は「おもいやる子」です。また、こんなことを言ったら、相手が悲しくなるかもしれないから言うのはやめようと気づく人も「おもいやる子」です。お母さんやお父さんがとても疲れているようだ、肩をもんであげよう、というやさしい気持ちのある子も「おもいやる子」です。皆さんは、きょうから「おもいやる子」になってください。
二つ目は、「き」です。これは「きたえる子」です。みなさんは遊びが大好きだと思います。外で思い切り遊ぶ子どもは、体が丈夫になります。また、かけっこや水泳や野球、サッカーなど運動やスポーツをする子も、「きたえる子」です。おおいに体をきたえる子になってほしいです。
「おもいやる子」「きたえる子」興本扇学園ではみなさんがそういう子どもになってほしいと思っています。
保護者のみなさまにお話します。お子様のご入学おめでとうございます。本日107名のお子さんをお迎えしましたが、小中一貫教育校のはじめての1年生ということになります。今日から9年間、本校で責任をもってお預かりいたします。みなさんの願いやご期待に応えられるように、私どもは精一杯努力をしますので、よろしくお願いいたします。子育ての中には、いろいろな悩んだり迷われることもおありかと思いますが、どうぞご遠慮なく相談いただきたいと思います。力を合わせて、おきもとおうぎの子どもにそだててまいりましょう。
本日ご臨席いただきました足立区教育委員会、地域の関係者の皆様、PTAの方々には、早朝より、新入生をお祝いくださいまして、誠にありがとうございます。心よりお礼申し上げます。地域の子どもたち、地域の中の学校に対して、今後ともご支援を賜りますようお願いもうしあげます。 本日はまことにおめでとうございました。 (砥抦敬三校長)
平成18年度 興本扇学園 足立区立扇中学校入学式式辞
新入生のみなさん、入学おめでとうございます。
本日は、足立区教育委員会はじめ、地域の関係の代表者の方々、PTAの方々など、多くのご来賓にきていただいております。ありがとうございます。 このほか、式場には、みなさんを育て、ようやく中学生になったことを一番喜んでくださっているお父さん、お母さんをはじめとする保護者の方々、みなさんの入学を心待ちにしていた、8年生、9年生のお兄さんやお姉さんたち、また、私ども学校の教職員一同も、みなさんの入学をこころから歓迎しています。
本校は、この4月から小中一貫教育校「興本扇学園」になり、開設式が昨日行われました。興本小学校と扇中学校が一緒になり、9年間教育を行うことになります。中学1年生は、7年生ということになります。新しい言い方に慣れるまで時間がかかるかも知れませんが、7年生と言われたら、みなさんのことです。
さて、これから興本扇学園で生活する上で、私から話したいことは2つあります。それは、「自立」と「責任」ということです。
「自立」という言葉は「自分で立つ」と書きます。つまり、人の世話にならず自分の力で立つ、独り立ちという意味があります。本当の意味での「社会的自立」は、仕事をもって働くこと、または成人になる二〇歳まで待たなければなりませんが、実はその準備を今日から始めなければいけないのです。自立にもいろいろありますが、身辺の自立はすでにできているでしょう。一人で寝たり起きたり、御飯を食べたり、着替えたり、排泄したりということは「身辺の自立」です。みなさんが、これからしなければならないのは「精神的自立」です。言い換えると「自分の頭で考えて行動する」ということです。
8年生、9年生の在校生が活躍する場面を、私は見ていますが、例えば、きのう行われた「対面式」では、代表の生徒が司会をして、会の進行を積極的に進めていました。また、毎年行われているサマーフェスティバルへの参加や11月に行われる扇祭などには、生徒のアイデアでいろいろが進められている様子が見られました。その基本は「自分の頭で考えて行動する」習慣があるから、そういう行動ができるのだと思います。その意味で、みなさんの先輩たちから多くのことを学んでください。
二つ目の話は「責任」ということです。「自立」という言葉とセットで考えてほしいのですが、自分の頭で考えて行動した、その結果については、自分で責任をとらなくてはいけないということです。勉強でも生活でも、自分でやったことは自分で責任をとることが求められます。これはある意味で厳しいことです。例えば、勉強を怠ければ成績が落ちます。わがままを言えば友だちが減ります。そういう結果がついてきますから、自分の頭で考える場合は、その結果責任まで考えてほしいということです。このことはみなさんがやがて社会で生きていく上では欠かせないことです。小学生から中学生になるということは、その準備が始まるのだということを心にとどめておいてください。
さて、最後になりましたが、新入生の保護者のみなさん、本日はおめでとうございます。中学生という多感な時期は、3年間と短いのですが、大人になろうと独り立ちする難しい時期でもあります。そこで、「自立」と「責任」の話をさせてもらったのですが、まずは大きく広く受け止めていただき、自分の頭で考えさせ、その上で「責任」があるところまで見届けてほしいと思います。生徒の考えで「責任」がとれそうもない場合は、親の出番が必要です。壁となって立ちはだかること、また人生の先輩として諭す場面が必要になることもあるかと思います。そのような時には、遠慮なく私どもにもご相談いただき、一緒に考えていきたいと思います。以上をもちまして、入学式の式辞といたします。
(砥抦敬三校長)
校長の砥抦です。小中一貫教育校「興本扇学園」としてスタートして1ヶ月が過ぎました。地域、保護者の皆さんには、今も毎朝、学園の前の通りの交通が激しいため、交通指導に立って、児童・生徒の安全確保をしていただいております。本当にありがとうございます。
学園としても、教師や生徒会の週番の生徒たちが、横断歩道や門のところで、朝のあいさつ運動をやりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
さて、この1ヶ月の児童・生徒の様子を報告いたします。私は東校舎と西校舎を行ったり来たりしておりますが、西校舎の方は、以前からみると、にぎやかになっただろうなと思います。5,6年生が増えたということですが、2階にある校長室にいても、上の方から、ガタガタと音がしてきます。机の移動が始まったかなと思いますが、時折廊下から、小学生らしい騒ぎ声が聞こえてきます。よく言えば活気があるということですが、小学生だからと言って甘やかしてはいけないなと思います。
5,6年生の授業の様子も見に行きましたが、今まで通りにやっていますし、休み時間(昼休み)になると、広い校庭に飛び出していきます。9年生らしい生徒たちとサッカーを一緒にやったりしている場面を見ると、なんだかうれしくなってしまいます。
担任からも報告を受けましたが、授業も45分から50分に延びましたが、特にそのことで気になる児童はほとんど見当たりませんでした。
雨が降っても、翌日晴れると広い校庭が思う存分使えるというのは、今までなかったことでしょう。
4月初めての朝礼と認証式が先日行われました。西校舎では、朝礼は毎週はありません。この時は、生徒会の委員の認証式も行われて、さすが中学生は態度が立派でした。しかし、5,6年生も負けてはいません。整列の仕方、挨拶の仕方、これも立派でした。代表委員の児童は「中央評議会」に参加して、7年生以上の生徒と一緒の会議に出ることになります。
5,6年生も、まだ多少緊張しているのかも知れませんが、元気にやっているなというのが私の印象です。
時々、またご報告いたします。


本日の議題
①1年生を迎える会の反省と改善点
②運動会スローガンアナウンスの反省と改善点
③運動会スローガン集計について
本日の委員会は、委員長が司会、副委員長が板書、書記が記録をしました。 これまでの活動の反省点として、「先生に頼りすぎずに活動できるようにする」という点があげられました。自分たちで委員会活動を創っていこうという意欲がすばらしいですね。
5月は運動会のスローガンのアンケート集計をします。担当を決めて各学年の先生方に聞きにいきます。 代表委員会は全校児童の前に出て活動する機会がこれからますます増えていきます。学校の顔として、これからの活躍を期待しています。
子どもたちの真剣な姿勢に感動した代表委員会担当より



小中一貫教育校初めての運動会が30日(火)に行われました。雨のため延期が続いておりましたが、この日は薄曇りで、午後は雷雨の恐れありという天候でしたが、かえって暑からずという運動会日和となりました。
地域の方たちも朝5時30分頃からつめてくださり、テントの立ち上げなどを手伝ってくださいました。本当にありがとうございました。
開会式では、児童・生徒代表の宣誓もあり、元気な声が校庭に響き渡りました。
各学年の徒競走、団体競技、演技なども順調に進み、予定の時間よりも早め早めに進行しました。これも、予行練習を行ったせいだと思います。来賓の方からも、子どもたちの動きが「キビキビしていて気持ちいいですね」というお褒めの言葉をいただきました。
色別対抗では、赤組が優勝しました。赤組おめでとう。でも、青組も黄組もがんばりました。一人一人が輝いていた運動会だったと思います。
地域、保護者、PTA役員の方々、大勢のご協力を得て、成功裡におえることができました。ありがとうございました。

今日は、職員会議の後で、学園のホームページを作成したり、更新したりする研修を行いました。
パソコンボランティアの方や慣れている先生が、初めての先生たちに教えています。先生たちも生徒になって一生懸命研修をしていることを報告します。

5・6年生の仮入部期間が続いています。今日は校庭で野球部が活動していました。職員室のベランダから見てみると、たくさんの5・6年生が野球部の体験に参加していました。練習ではキャッチボール、トスバッティングのあと、5・6年生がランナーになって中学生が守備につくという試合形式のノックが行われました。とくに5年生は先輩のいるグラウンドでかなり緊張しているようでした。


みんなが待ち望んでいたプールに、今日入ることができました。授業が始まるころには、日が出てきたので、冷たい水が心地よく感じました。バディ、水慣れ、流れるプールなどを行い、授業を終えました。プールサイドでの過ごし方、話を聞く姿勢も、去年より上達しています。
今年初めてプールに入った感想は・・・
「流れるプールが楽しい!」
「水が冷たくて気持ちよかった!」
「金曜日に2時間の授業だから、早く金曜日になってほしい。」
流れるプールでみんなと一緒に泳いだ担任より


7月5日から7日まで、9年生の職場体験が行われました。上級学校、会社、お店、保育園、コンビニなど働いてみたい職場を探して、3日間の体験学習を行いました。興本小学校にも、学級の方に3名、用務の方に3名の生徒が体験しました。
1,2年生の学級に先生のアシスタントという形で指導の補助をしました。休み時間などには、子ども達が「おおきいお姉さん」のとりっこをしていたそうです。
用務の仕事体験をした生徒は、モップで廊下を掃除したり、木の枝を切り落としたり、そのゴミをまとめて出したり、結構大変そうでした。文字通り、額に汗して・・・という体験でした。
後ほど、生徒はこれらの体験をまとめて発表します。どんな感想を述べるか、楽しみです。


地域の方のご好意により、ジャガイモ掘りを体験しました。ジャガイモはアサガオのように種をまくのではなく、またサツマイモのようになえを植えるのでもなく、ジャガイモそのものを植えることをおじいさんの話から知りました。
畑で掘り始めると、大きなジャガイモが出るたびに、大きな歓声を上げていました。次々に掘り出されるジャガイモで、あっという間に用意した袋は一杯になりました。子どもも教員も夢中になれた楽しい時間でした。


7月28日は全日、品川区立日野学園で開かれた小中一貫教育全国サミットに参加してきました。午前中は、品川、呉、京都、奈良の教育長と文部科学省の前川課長、それにコーディネーターの天笠先生の6名で、各市区の現状と課題の報告がありました。教育長自らリーダーシップを発揮しているところは共通でした。
午後は、分科会で「学校組織・運営分科会」に出ました。この11月に視察予定の奈良市立田原小中学校の校長先生の発表もあり、自然な姿を話されていました。小中の教員の意思疎通が問題だという指摘がありましたが、どこも、文化の違いというような課題はあるようです。
最後に兵庫教育大の梶田先生の講演がありました。今の教育改革の根底には、全国共通の基準づくりと、その地域に最適の基準の両方が必要であるというお話と、終わり頃には学習指導要領の改訂の最新情報のお話もありました。また、子どもに付けたい力は、いわゆる世の中を生きる力と、与えられた自分の命をどう生きるかという個人の生き方を教えることであると締めくくられました。
各学年の参加者(お父さん方・先生方)は、みなさん「優勝!」「必勝!」を目標に、とてもいきいきとしていて楽しそうでした。みなさんお疲れ様でした。5年生チームはブロック大会もがんばってください!





6年生が日光でいなくて、中学生は期末テスト中。3時間目以降は西校舎に5年生しかいない日が続いています。そんなこともあって今日は、中学校の先生方を迎えて盛大にバイキング給食が行われました。各テーブルに様々な料理が運ばれ、いつもとはちがった給食で、子ども達も嬉しそうに食べていました。給食室の方々、栄養士の先生、5年生のために本当にありがとうございました。中学校の先生方もお忙しい中、来てくださりありがとうございました。思い出に残ったバイキング給食でした。


足立区教育委員会に設置されている小中一貫教育指導委員会が、本学園が会場となり行われました。早稲田大学の安彦先生、筑波大学の根津先生、東京都教育委員会の伊東先生など委員の先生方には、5時間目の授業を見ていただき、後ほど、講評をいただきました。落ち着いた授業の雰囲気であったことなどをほめていただき、問題点としては、子どもたちの活動に活発さがほしいということがあげられました。今後の課題としていきます。
指導委員会としては、興本扇学園のこの6ヶ月の様子(生徒会活動、部活動、交流授業など)を、ビデオで映しながら近藤主幹が説明いたしました。
今日の3校時、本校初めての、1年生と8年生の合同体育が行われました。




8年生は、柔道で自己の体格や体力に適した技を身につけ、相手の動きに対応した練習や試合を楽しむことをねらいとしています。1年生は、からだほぐし運動でからだの基本の動きができるようにすることをねらいとしています。始める時や終わる時の礼儀作法も大事なポイントです。また、8年生が1年生の児童に技のポイントを教える場面が随所に見られました。
8年生の優しい表情がまた素晴らしいですね。1年生も、最後に、「ありがとうございました。」と大きな声でお礼が言えました。



11月2日、3日の2日間にわたり、興本扇学園の第一回学園祭が盛大に開催されました。 1年生の可愛い合唱や合奏にはじまり、9年生の立派で洗練された合唱や演劇まで、盛りだくさんの内容でした。 一つ一つの学年、一人一人の児童・生徒が心を込めて発表し、会場内が大きな感動で包まれました。
 11月12日(日)、興本扇学園開設記念式典・祝賀会が行われました。
鈴木区長をはじめとして、政治家の方々(国・都・区会議員)町会・自治会関係者、地域の協力者、現役のPTAとOB、歴代校長、区内の校長、現・旧職員等々、総勢約310名の参加があり、大変心温まる会になりました。(写真・編集:田中主幹)
11月12日(日)、興本扇学園開設記念式典・祝賀会が行われました。
鈴木区長をはじめとして、政治家の方々(国・都・区会議員)町会・自治会関係者、地域の協力者、現役のPTAとOB、歴代校長、区内の校長、現・旧職員等々、総勢約310名の参加があり、大変心温まる会になりました。(写真・編集:田中主幹)
-式典の様子-








-祝賀会の様子-











雨で延期されていた1,2年生の遠足が行われました。天気は最高。風もほとんどなく、暖かい一日でした。2年生が1年生の面倒をみるということで、バスの中も、席を1年生に譲っていました。バスから降りて、歩く時も2年生が手を引いてあげていました。優しい2年生です。
水元公園の広場に到着すると、まずは、グループごとに思い切り遊びました。追いかけっこ、リレー、縄跳び、ボール遊び、影踏み等々、用意してきた遊び、または周りを見ていておもしろそうと思った遊びを始めました。子どもはこうでなくちゃ・・・。ところが、グループに入らないで、じっとしている子もいました。「どうしたの?」声をかけると、「朝ごはん食べてないから、元気が出ない。」とのこと。「そうか、もうすぐ、お弁当だから元気出してね。」
昼食の合図の笛が鳴ると一斉に食べ始めます。
午後は、秋を拾おうということで、木の実や紅い葉っぱを拾い集めました。後で、授業で使うのだそうです。ビニールの袋がだんだんふくらんできます。
最後は、山で遊びました。滑り台をすべりおりたり、坂をわざと転げ落ちたり、楽しそうなこどもたち。怪我だけはしないでと、ハラハラドキドキの私たち。
みんな元気に帰って来ました。2年生の優しさが印象的な遠足でした。 (砥抦敬三校長)


今日は和風料理の給食です。
ごはんは鮭を焼いてほぐし、酢めしに混ぜました。その他ごはんにはいり卵とゆでたさやいんげん、白ゴマも入れました。
鮭の塩味が効いてとてもおいしく、かつ赤、黄色、緑と色合いもきれいに仕上がりました。
今日は7年生の教室にいきました。みんな良く食べてごはんはすべて配られ、食缶には残っていませんでした。
おかずは「揚げだし豆腐」です。配膳中に「これなあに?」と聞く生徒がいました。そうするとすぐに「これ豆腐でおいしいんだよ。」と答えてくれる生徒がいました。給食は子どもどうしのコミュニケーションの題材にもなっています。
また学校給食ではいろいろな料理や食材を知るという目的もあります。
今日の「揚げだし豆腐」の上には「ししとうがらし」を素揚げしたものをのせました。「ししとうがらし」がわからず「これ何。」と聞いている子どももいました。
西校舎では5年生から9年生の給食ですので、大人の味に近づけた料理を取り入れるようにしています。
料理に対する知識を広げてもらうためにも、これからもいろいろな料理に挑戦して出していきたいと思います。


夏休みの読書感想文の学年代表の児童に校長先生から、賞状をわたしてもらいました。これからも、みんなが良い本をたくさん読んでほしいと思います。そして、良い本をみんなに紹介してほしいです。本は心の栄養です。みなさんの心がその栄養で豊かになるといいですね。
また、養護の先生から、風邪の予防のお話がありました。せきをすると、こんなに風邪の菌が飛びます。テープで見えるように示してくれました。マスクをしたり、口を手でおおったりすると良いですね。また、風邪を引かない強い体を作りましょう。そのためには、元気に遊ぶ、しっかり食べる、良く寝る。ということが大切です。風邪のはやる季節になってきましたが、興本扇学園の子は、元気に乗りこえてほしいと思います。
子どもに負けたくない、元気な副校長より (浅川副校長)
平成18年度 東京都中学校ロボットコンテスト、「二足歩行スプリンター部門」において、本校生徒が1・2・4位を獲得しました!おめでとう!



<参加生徒のコメント>
私たち「選択技術」は、ゆかいな先生1名とその仲間たち7名で活動しています。
私たちの目標は、「東京都ものづくりフェア in Tokyo」で毎年行われている「東京都ロボットコンテスト」に出場することです。ロボコンに出場したのは、今年で2回目ですが、1年目・2年目ともに1位・2位を独占するほどの強者揃いです。
しかし、コンテストを離れると、ロボット作りをしているときもたいへんゆかいな人たちになります。『能ある鷹はつめを隠す』とはこういうことを言うのでしょうか。
「選択技術」は、9年生になってから学習します。ロボコン後継者がいないので、すごくピンチなんです。誰かやる気のある人が現れるといいな、と思うこの頃です。


寒い時期にも、元気に外遊びをしよう!と言う目的に合わせて、全校で大縄跳びに取り組んできました。クラスのみんなが一緒になって遊ぶ姿も、とても素敵でした。
さて、本日、集会の時間に、1年生から4年生まで2分間で何回跳べるかを競争する、大縄跳び大会がありました。低学年は波跳び、中学年は八の字跳びでの挑戦でした。最高記録は、4年生の139回。高速スピードで跳んでいくその姿は、さすが東校舎の最高学年!と言う印象でした。
大縄回しで肩が少し重い4年担任より


ビニールを使って、凧(たこ)を作りました。さあ、外であげてみよう。
風の具合もちょうどよく、みんなで凧揚げを楽しみました。問題は、お友だちの凧と絡んでしまい、糸がなかなかほぐれないことです。先生たちが修理屋さんになって、行列ができるほどでした。浅川副校長先生、金子先生(西校舎)、お手伝いありがとうございました。


興本扇学園の統一校章が入った半袖体育着(丸首Tシャツ・白)ができました。 小学校と中学校のPTAの本部役員の方々にも意見をいただきながら、素材・デザイン・価格・耐久性などを考慮して、数社のものから選びました。 平成19年度、第1学年と第7学年は全員着用、他の学年は従来のものでも新しいものでも着用可とします。 なお、第1学年~第6学年の名札・黄帽も来年度より、統一校章の入ったものに変更になります。新体育着と同じ扱いになります。


本校のS先生が東京都の教師道場の研修に参加していますが、今日は、そのグループの研究授業が行われました。7年生の一つのクラスで、「A Letter from the UK」という単元を扱い、教師道場の教授、指導教諭、研修仲間の先生たち、本校の先生が参観しました。
あいさつ、ビンゴ、チャット、ワードテスト、ピクチヤーカードなど、多様な学習材が用意され、S先生のテンポのよい展開に、生徒たちもだんだん気持ちがのってきて、楽しい雰囲気になってきました。繰り返し発音させることで、耳になれ、口にも出して体験的に覚える様子が、見ている私たちにも伝わってくる、いい授業でした。


「Your name, please?」、「Thank you.」と6年生の英語が中学生の教室のあちらこちらで聞こえていました。2月20日(火)、帰りの学活で、今まで学習してきた英語表現を使って、7,8年生に英語インタビューをしました。中学生も6年生も少し緊張気味で、ドキドキしながら、英語を発音していました。みんな、初対面の人もいる中で、スムーズにインタビューをし、自信をつけていたようです。
感想には、「中学生の発音が良かった。」、「東校舎では味わえない貴重な経験をした。」というような前向きな言葉が見られ、6年生にとって、自分たちが学んできた英語を話す絶好の機会となりました。



今日は中学校の卒業式でした。気温は低いが天気は上々です。9時にモーニングに着替え、式辞は内ポケットに入れました。9年生の担任に、「おめでとう。」を言いました。風邪で休む生徒だけが心配です。
来賓の方々に挨拶し、開式10分前に式場へ案内しました。式場には、すでに、5年生から8年生、保護者の方々が着席し、凛とした雰囲気が漂っていました。
いよいよ9年生が入場。44名の卒業生。担任が先頭になり、厳かに入場。教務主任の司会で、式が始まりました。「平成18年度興本扇学園足立区立扇中学校、卒業式を挙行いたします。」国歌斉唱、区歌斉唱、学事報告と続き、「卒業証書授与!」という段になり、私が緊張した面持ちで登壇します。
最初の生徒の名前が読み上げられ正面から登壇した。「卒業証書、(名前)中学校の全課程を修了したことを証する。平成19年3月20日、(校長名)(台帳の番号)」
「おめでとう!」と一人一人に声をかけました。最後の生徒は、再び全文を読み上げてから渡しました。皆立派な態度で受け取っていました。
式辞は以下の通りです。
卒業式式辞
卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。皆さんは、義務教育の9年間を終えて、これからは、自分の意思で勉強したり、働いたりするわけです。義務教育というのは、国で、あるいは、保護者の人が、一人前になるためには、これだけのことを身につけておいてほしいという意味で、9年間の教育を受けてもらったのです。ところがこれからは、ちがいます。教育を受けるのは義務ではなく、やりたい人は勉強したり、働いたり、自由なのです。当然のことながら、自由の裏側には責任というものがついてきます。
皆さんはそういう大人の社会に一歩踏み出すのです。
さて、ここで、卒業される皆さんに、一つ考えてほしいことをお話します。それは、私が障害のある子どもたちの教育にかかわるようになって、こころの奥で、いつも考えてきたことです。
それは、私たちが「生きる意味」は何かという、大変難しい話です。でも、どこかで、皆さんも、つらいときや、自分のことを振り返ったりした時に、フッとそういうことを考えることがあると思うのです。何のために自分は生きているのだろうか、「生きる意味」は何かということも、私も考えました。
そういうときに一さつの本を通して、一人の人と出会いました。それはフランクルという精神医学者です。歴史に詳しい人は分かるかもしれませんが、アウシュビッツという収容所で生きるか死ぬかのギリギリの体験を「夜と霧」という本に書いたことで有名な人です。そのフランクルという人が、生きる意味について、人生には三つの価値があると言うことを言っています。それは、「創造価値」と「体験価値」と「態度価値」であるということを言っています。
はじめの「創造価値」というのは、簡単に言うと、ものを作り出すということですから、働くことに生き甲斐を見いだすことです。自分のしごとに誇りをもって働くということです。これは大事なことですよね。
次の「体験価値」というのは、自然や芸術や人間を愛することによって得られるものです。美しい絵や音楽を鑑賞したり、人を愛することによって人生の素晴らしさを体験したりすることです。これも人生において大事なことです。
最後の「態度価値」というのは、運命とかさけられない事実を前にして、どんな態度をとるかによって価値が決まってくるというものです。例えば、死ぬ間際の患者さんが医者のことを思いやるとか、つらいことから逃げないで、事実として引き受ける姿勢に、その人の生き方が高められるというのです。 そしてフランクルは、この3つの中で、一番大事なものはこの「態度価値」であるとも言っています。皆さんもこれから、人生の悩みやつらいときもあるでしょう。そういうときにこの「態度価値」を思い出してください。どのようなつらい時でも、自分の人生は自分で切り開いていく、人にやさしくできる、前向きに笑顔で取り組んでいく、そういうことを期待して、はなむけの言葉といたします。
保護者の皆様も、本日生徒さんたちが、りっぱに卒業証書を手にされる様子をごらんになって感慨深いものがおありかと思います。心よりお祝い申し上げます。この間、小中一貫校の開設ということで、保護者の皆様にもご心配をおかけし、また様々なお力添えをいただき、1年間が経過しました。感謝申し上げます。お子さんたちは第1回の卒業生となるわけですが、今後とも、お子さんともども、学園を見守っていただきますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、ご来賓・地域の方々にご挨拶申し上げます。この間一貫して、本学園を支えていただきありがとうございました。ほとんどの卒業生は、この地域に生まれ、この地域で育った生徒たちです。どうかこれからも、地域の活動などに生徒を参加させていただき、ご指導いただければ幸いです。興本扇学園はまだ1年生ですが、これからますます発展してまいります。今後とも、ご支援のほどお願い申し上げ、式辞といたします。
その後来賓の教育委員会Iさん、地域代表の前町会長Eさん、PTA会長の祝辞をいただきました。
在校生代表の送る言葉と歌。卒業生代表の言葉や歌が始まると、あちこちですすり泣きが始まり、最初は女子から、次第に男子にも広がり、歌は女子が支えていたほどに、男子生徒は泣き出して歌う声が聞こえないほどです。隣では担任もすすり始めるし、校歌斉唱の時には、私も駄目でした。
式は無事に終了し、心に残る卒業式でした。(風邪のため欠席は1人。後日、一人だけの卒業式をやりました)
今日は、興本小学校の卒業式でした。私にとっては、4回目になります。卒業する6年生、98名。3年生の時に赴任したので、4年間つきあった子どもたちです。
来賓の方々も大勢来てくださいました。予定通り9時50分に、来賓の方々をご案内して入場しました。ところが、私が勘違いして、職員席の方に案内してしまい、途中で気づき、来賓席の方に戻りました。初めから、あがってしまいました。
落ち着いた態度で、6年生が入場しました。もうこの時点で、涙が出そうになりました。今年はおかしいのです。
国歌、区歌を歌い、卒業証書授与となり、登壇しました。中学校と同じように、最初の子どもと最後の子どもの証書のみ読み上げました。本当は全員のものを読み上げるべきですが、時間の関係で仕方ありません。あとは、担任が呼名するだけで、渡していきます。
「卒業おめでとう。」と小さい声で私がかけていくと、「ありがとうございます。」とほとんどの卒業生が返してくれました。それで、またジーンときてしまいました。個別の話題のあった子には、一言付け加え、「がんばってね。」と声をかけました。
次ぎに式辞を読みました。多少アドリブが入りましたが、用意した原稿どおりに読まないと、話が飛んでいってしまうからです。とにかく、つかえないように注意し、最後に日にち、名前まで読み上げました。
卒業式式辞
『 春の訪れを感じさせる今日のよき日、本校第四五回の卒業生として、卒業される98名のみなさん、ご卒業おめでとうございます。 また、本日は、みなさんの卒業をお祝いするために、足立区教育委員会市川様、町会、自治会の会長様、PTAの方々はじめ、多くのご来賓の皆様が、この席に来てくださいました。まことにありがとうございます。
さて、卒業証書を受け取るときの、皆さんの顔をみていましたら、みなさんが小学校に入学した頃と比べると大きく成長したな、これからもがんばってほしいという思いで、一人一人に声をかけました。 義務教育の六年間が修了したわけですが、お世話になった様々な人を思い浮かべてください。お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、交通指導員の方々、町会の方々、学校の先生、主事さんたち、そのほか地域の方々にもお世話になった方が大勢いるとおもいますが、「無事卒業しました。ありがとうございました。」と声をかけてください。自分の気持ちは、声に出して相手に伝えることが大切です。うまく言葉にならない人もいるでしょう。その人は、手紙に書いて、短い言葉でもいいですから、思いを伝えましょう。
さて、卒業されるみなさんが、これから中学校生活を充実させ、楽しく送るために役立ててほしいと思う話をします。
一つ目は、「夢中になれるものをみつけましょう」ということです。すでに中学校の部活動に参加している人もいます。また、和太鼓に夢中になっている人もいます。「夢中になれるもの」が、なぜ大切かというと、その理由は三つあります。一つは「心や体が鍛えられ」ます。二つ目は「集中力」が身に付きます。最後に、いやなことがあっても忘れることができます。そういう意味で、「夢中になれるもの」をみつけてほしいのです。
二つ目は「自信」です。自分だってやればできるんだという自信が大切です。同じ能力を持っているひとでも、自信がある人と、ない人では、結果がちがってきます。誰でも完全な人はいません。みんな欠点・短所があります。でも、一つのことに自信を持つと、ほかのこともできるようになるから不思議です。「やればできるんだ」という体験をどんどんしてほしいと思います。
最後は「思いやり」です。気遣いとも言います。相手の立場に立って考えてあげられる能力です。今、どんな言葉かけをしてあげたら良いのかなと、ちょっと相手の立場にたってみることです。きっと「豊かな心の時間」でも勉強した事と思います。教室の中の勉強だけではなく、実行することが大事です。感謝の気持ちをもっていても、言葉にして相手につたえなければ、分かってもらえません。
以上、「夢中になれるもの」「自信」「思いやり」の三つをはなむけの言葉といたします。皆さんの中学校生活に期待しています。
さて、保護者の皆様にご挨拶もうしあげます。本日はまことにおめでとうございます。ここに義務教育の前半を無事に終えて、卒業ということになりました。心よりお祝いを申し上げます。昨年、興本扇学園として開設し、ようやく一年がたちます。開設に際しましては、いろいろなご協力・ご支援をいただきまして、本当にありがとうございました。私どももいたらないことが多々あったとことと思いますが、本校に対して変わることなく深いご理解とご協力を賜りましたことを心よりお礼申し上げます。
これからも思春期の子どもたちですから、いろいろな社会の荒波ばかりではなく、こころの葛藤なども経験する難しい時期でもあります。どうか今後とも、子どもたちを温かく見守っていただきたいと思います。本日はまことにおめでとうございます。
平成19年3月23日
興本扇学園足立区立興本小学校長 砥抦敬三 』
呼びかけが始まり、歌が始まると、これが泣かせる曲ゆえ、涙腺がゆるみっぱなしでした。女の子、男の子、数は少ないが、泣いていました。
校庭で親子で学級ごとの写真を撮りました。春の陽差しが暖かかったです。
卒業生のみなさん、がんばってください。卒業おめでとう